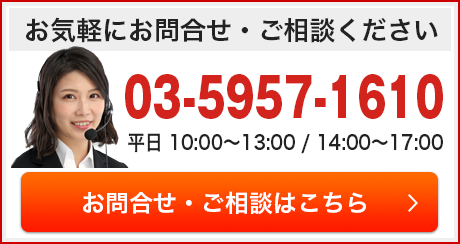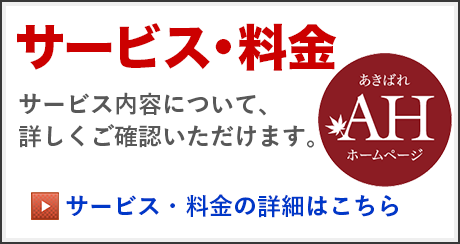正しい知識を身につけるのと同じくらい大切なのが、「よくある失敗」を知り、それを避けること。それは、SEOにおいても同じです。
【基礎編】の最終回となる第5回では、多くのSEO初心者がついやってしまいがちな失敗例や、絶対に手を出してはいけないNGパターンを具体的に解説します。
あなたのこれからの努力を確かな成果につなげるために、ぜひ最後までお読みください。
【この記事で分かること】
- 初心者が陥りやすいSEOの誤解や失敗例がわかる
- サイト評価を下げる「やってはいけないNG行動」を理解できる
- 遠回りせず、正しい方向でSEOを続けるためのヒントが得られる
失敗1.キーワードを意識しすぎる

SEOを学び始めると、誰もが「キーワードが重要だ」と教わります。もちろんそれは事実です。しかし、その重要性を意識しすぎるあまり、キーワードを詰め込むことばかりに気を取られてしまうことがあります。
キーワードの役割は「検索する人と、その答えを持つページを結びつける手がかり」です。
ところが、この本来の目的を見失い、とにかくキーワードをたくさん使えば良いと考えてページを作成してしまうと、かえって評価を下げる結果になってしまいます。
これが、初心者が最も陥りやすい失敗です。
不自然にキーワードを繰り返す
上位表示させたいキーワードがあるからといって、記事のタイトルや本文に同じキーワードを何度も不自然に繰り返すのは逆効果です。
以下のような「キーワードの詰め込み」は、非常に読みにくく、不自然な印象を与えます。
| 悪い例 | SEO対策でSEO効果を上げるSEO方法をSEO初心者に解説 |
| 良い例 | SEO対策の効果を上げる方法を初心者向けに解説 |
ページを検索してたどり着いた人が、「この文章は読みにくい」と感じてすぐに離脱してしまえば、読者がそのページに留まる「滞在時間」は短くなります。
すぐに離脱されてしまうサイトは、Googleに「役に立たなかったページ」と判断され評価が下がり、検索順位にも悪影響が出てしまう可能性があります。
関連性の低いキーワードを無理に詰め込む
検索される回数が多いキーワードだからといって、内容の本筋とは関係ないキーワードを無理やり文章に入れるのもよくある失敗です。
例えば、「肩こり解消ストレッチ」のページなのに、「腰痛」や「整体 おすすめ」といったキーワードを無理に入れると、読者は「この文章は、結局何が言いたいの?」と混乱してしまいます。
これはGoogleも同じで、テーマがぼやけてしまうと、「このページは何について書かれているのか」を正しく判断できなくなります。その結果、本来なら上位表示されるべきキーワードでも、評価が下がってしまうことがあるのです。
正しいキーワードの使い方
キーワードを必要以上に文章に組み込む必要はありません。自然で読みやすい文章の中に、文章として読みやすい範囲で含める程度で十分です。
まずは「読者が理解しやすい文章」を心がけ、その中で自然にキーワードが登場するようなページ作成を目指しましょう。
失敗2.読者の「知りたいこと」を無視する

第4回で解説した通り、SEOで最も大切なのは「検索する人の気持ちを考える」ことでした。この読者目線を忘れてしまうと、たとえあなたが素晴らしい情報を持っていたとしても、読者の満足を得ることはできません。
ここでは、そうした「読者とのすれ違い」が起きてしまう、具体的な失敗例を見ていきましょう。
自分の「書きたいこと」だけを書く
「自分の知識を詳しく伝えたい!」という情熱を持つのは素晴らしいことです。しかし、その「伝えたいこと」と検索する人の「知りたいこと」は同じ内容でしょうか?
自分が書きたいことだけをそのまま載せると、検索する人の知りたい情報とはズレてしまう場合があります。
例えば、整体師が「最新の施術法の高度な理論」について熱心に解説したページを作成しても、検索した人の多くが「まずはこの肩こりを、簡単になんとかする方法」を知りたいと考えていれば、そのページは読者の満足を得られません。
読者が求める情報とズレていると、ページの滞在時間は短くなってしまいます。その結果、Googleに「役に立たないページ」と判断され、検索順位の低下につながります。
難しい言葉や専門用語ばかり使ってしまう
自分の専門性を伝えたい気持ちが強すぎると、無意識のうちに難しい言葉や専門用語ばかりを使ってしまいがちです。
しかし、ページを見るのは、あなたと同じレベルの知識を持った専門家ではありません。専門用語が多すぎると、読者は内容を理解できず、「この記事は自分向けではなかった」と感じてすぐにページを離れてしまいます。
専門用語はできるだけ分かりやすい言葉に言い換える、どうしても使う必要がある場合は簡単な補足説明を加える、といった工夫が大切です。
例えば、「インデックス(検索エンジンのデータベースに登録されること)」のように、カッコ書きで補足するだけでも、読者の理解度は大きく変わります。
読者の気持ちを理解するコツ
ページを作成する前に、「この検索をする人は、どんなことに困っているのか?」「どのくらいの知識レベルの人なのか?」を想像してみましょう。
検索キーワードから読者の状況を推測し、その人が本当に求めている答えを、相手のレベルに合わせた分かりやすい言葉で提供することを意識してみてください。
専門的な知識であったとしても、きちんと読者が理解できる形で伝えるページをつくる。それがSEOで成果を出すための第一歩です。
失敗3.「とりあえず記事を書けばいい」と考える

SEOについて調べると、「まずは記事をたくさん書きましょう」というアドバイスをよく見かけます。
もちろん、サイトの情報量を増やすことは大切ですが、この言葉を「質より量」と勘違いしてしまうと、大きな失敗につながります。SEOにおいて重視されるのは、あくまでも「記事の質」です。
質の低い記事の量産は、SEOの失敗の原因になってしまいます。
内容の薄い記事を量産する
量を重視した結果、よくある失敗は「内容の薄い記事」を数多く作ってしまうことです。
例えば、「〇〇とは、△△のことです。」のように数行の説明だけで終わっていたり、誰でも知っているような当たり前の情報ばかりのページがこれにあたります。
Googleは「読者の悩みを解決できるか」を重視するため、このような役に立たないページは評価されません。
それどころか、サイト内に質の低いページがたくさんあると、「このサイトは全体的に品質が低い」と判断されます。そして、せっかく作った質の高いページの評価まで下がってしまう可能性もあるのです。
記事を書いたまま放置する
一度公開したページを、その後まったく見直さずに放置してしまうのも、よくある失敗の一つです。
どれだけ素晴らしい内容でも、時間が経てば情報は古くなります。特に、商品の価格やお店の営業時間、法律や制度に関するデータなどは、変化しやすい情報の代表例です。
古い情報のまま放置されたページは、読者にとって価値が低いだけでなく、サイト全体の信頼性にも影響します。
また、Googleも情報の「鮮度」を重視しているため、定期的な更新や見直しが行われていない場合、サイトの評価にも影響が出ることもあります。
他サイトのコンテンツをコピーする【絶対NG】
「質より量」という考え方で最も陥りやすいのが、他のサイトの文章をそのまま、あるいは少しだけ手を加えて自分のサイトに掲載する「コピーコンテンツ」です。
これは、著作権の問題になる可能性があるだけでなく、SEOにおいても絶対にやってはいけない行為です。
Googleは、「オリジナル性(独自性)」を非常に重視しており、コピーされたコンテンツは「価値のないページ」と判断します。
コピーコンテンツを作成した結果、検索順位が大幅に下がったり、検索結果に全く表示されなくなったりといった、厳しいペナルティを受けるリスクが高まります。
質の高い記事を作るための基本
記事を作る際は「この内容で、検索する人の悩みは本当に解決できるだろうか?」と自問してみてください。また、公開後も定期的に内容を見直し、新しい情報の追加や古い情報の更新を行う習慣をつけましょう。
サイト全体の価値を着実に高めるためには、一度書いて終わりにするのではなく、育てるように少しずつ改善を続けることが大切です。
失敗4.すぐに結果を求めて、諦めてしまう

これまでの講座でも触れてきた通り、SEOは時間をかけてサイトの価値を積み上げていく、長期的な取り組みです。
焦ってすぐに結果を求めてしまうと、多くの場合、失敗に終わります。焦りから生まれる、具体的な失敗パターンを見ていきましょう。
公開直後に順位を気にする
ページを公開すると、「早く順位が上がってほしい!」と、日に何度も検索結果をチェックしたくなりがちです。しかし、公開してすぐに順位を気にしすぎる必要はありません。
なぜなら、公開されたページがGoogleに認識され、データベースに登録される(インデックス)までには、そもそも一定の時間がかかるからです。検索で安定した順位に表示されるまでには、早くても1週間、通常は1ヶ月以上かかることもあります。
公開直後は順位を気にするよりも、誤字脱字がないかを見直したり、他の関連記事からリンクを貼ったりと、ページ自体の質を高める作業に集中しましょう。
結果が出ないと更新をやめる
「なかなか順位が上がらないから」といって、ページの更新や改善作業をやめてしまうのが、最も多く、そして致命的な失敗です。
繰り返しお伝えしてきた通り、SEOは長期戦です。成果が出ないからと諦めてしまえば、それまでの努力もすべて水の泡になってしまいます。
アクセスが少ないページでも、タイトルを見直したり、最新情報を追記したりといった小さな改善を続けることが重要です。その地道な取り組みの積み重ねこそが、Googleからの評価を高め、数ヶ月後に大きな成果となって返ってくるのです。
SEOを継続するための心構え
SEOは「今日頑張ったから、明日結果が出る」ものではありません。しかし、月に1回程度でも、サイトを見直して小さな改善を積み重ねることで、半年後、1年後には大きな変化を実感できるはずです。
「継続」ができるかどうかが、SEOで成果を出すための分かれ道です。自分で無理なく続けられる工夫をしたり、小さなルールを決めたりして、コツコツと取り組んでいきましょう。
失敗5.外部対策にばかり気を取られる
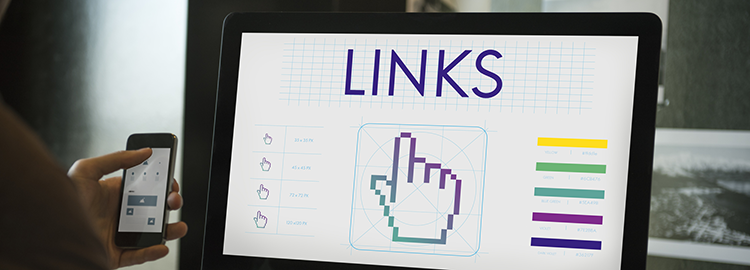
SEOを学び始めると「被リンクが大事」という情報をよく目にするかもしれません。
そうすると、サイトの中身を充実させる「内部対策」をおろそかにして、外部リンクの数を増やす「外部対策」ばかりに気を取られてしまう、という失敗がよくあります。
第3回で解説した通り、SEOの基本は「良い中身が良い評判を呼ぶ」という順番です。その順番を無視した、間違った外部対策について解説します。
相互リンクばかりに頼る
相互リンクとは、ホームページの運営者同士が、お互いのサイトにリンクを貼り合うことです。
相互リンクを増やすとSEOに良さそうに見えますが、「リンクの数を増やせば順位が上がる」という考えだけで、自分のサイトと全く関係のないサイトとリンクを交換するのは間違いです。
Googleはリンクの「数」だけでなく、「質」と「関連性」を非常に重視しています。あなたのサイトの内容と全く関係のないページからのリンクは、読者にとっても価値がなく、Googleからも評価されません。
それどころか、不自然な相互リンクが多いと、検索エンジンが禁止している不正行為と見なされてペナルティを受けるリスクさえあります。
無駄なリンク集や掲示板に登録する
一昔前は、自分のサイトのリンクを様々な「リンク集サイト」や掲示板に登録し、外部リンクを増やすというSEOの手法がありました。しかし、これは今では間違った方法のひとつです。
誰でも登録できるようなリンク集や、あなたのサイトとは全く関係のない掲示板からのリンクは、リンクの「質」を重視するGoogleにとって「価値の低いリンク」と見なされます。
SEO効果はほとんどないどころか、質の低いサイトからのリンクが増えすぎると、あなたのサイトの信頼性が下がり、検索順位が下がってしまうリスクもあります。
有料リンクを購入する【絶対NG】
「お金を払って、他のサイトから自分のサイトへリンクを貼ってもらう」という外部リンクの増やし方は、Googleがガイドラインで明確に禁止している、最もリスクの高い行為の一つです。
一時的に検索順位が上がることがあっても、Googleのシステムが不正なリンクだと検知した場合、厳しいペナルティが課されます。
ペナルティを受けると、順位が大幅に下がるだけでなく、最悪の場合、検索結果に全く表示されなくなる可能性もあります。一度失った信頼を回復するのは、非常に困難です。
健全な外部リンクの増やし方
外部リンクは無理に増やすものではなく、良質なコンテンツを作り続けることで自然に獲得されるものです。
読んだ人が他の人にも教えたくなるような記事や、同じ業界の専門家が参考資料として引用したくなるような内容など、読者にとって本当に価値のある情報の発信を続けましょう。
それが結果的に、他のサイトから自然に紹介される「価値あるサイト」へと成長させてくれます。
絶対避けたい!致命的なNGパターン

これまでに解説してきた失敗例は、主にSEOにとって「サイトの評価が上がりにくくなる」ものでした。
しかし、SEOの世界には、サイト全体に深刻なダメージを与え、最悪の場合、検索結果に表示もされなくなる「致命的なNGパターン」が存在します。
最後に、そうした絶対に避けるべき危険な行為を厳選して解説します。あなたのサイトを守るために、必ず覚えておいてください。
検索結果から消される恐れのある行為
Googleのペナルティの中でも最も重いのが、サイトが検索結果から完全に除外されてしまう、「インデックス削除」です。
インデックス削除されてしまう可能性が特に高いのが、以下のような、読者や検索エンジンを騙すことを目的とした行為です。
- 他サイトのコンテンツのコピー・無断転載
- 有料リンクサービスの購入・利用
- 偽のサイトを大量に作って自分でリンクを貼る行為(自作自演)
これらの行為は、検索エンジンが禁止している「スパム行為(不正な手法で検索順位を操作しようとする行為)」に該当し、Googleのガイドラインに対する明確な違反と見なされます。
一度このペナルティを受けると、検索順位の回復には数ヶ月から、場合によっては数年単位の時間がかかることもあり、当然その間はあなたのホームページは検索結果に表示されない可能性があります。ビジネスに与えるダメージは非常に大きいと考えてください。
サイト全体に悪影響を与える行為
検索結果から消されるほどのペナルティではありませんが、サイト全体の評価を徐々に下げてしまう危険な行為も存在します。それは、「質の低いページをサイト内に大量に作成してしまう」ことです。
具体的には、以下のような行為が該当します。
- 内容の薄いページを大量に作る
- キーワードだけを少し変えた、中身がほぼ同じページを量産する
- 自動生成ツールなどで作られた、意味の通らない文章を投稿する
サイト内に質の低いページがあると、そのページがサイト全体の足を引っ張り、他のコンテンツやサイト全体の評価まで下げてしまうことがあるのです。
取り返しのつかない変更
技術的で少し難しい話になりますが、サイトの評価をゼロに戻してしまう可能性のある「取り返しのつかない変更」もあります。
サイトを長く運営していく中で、Googleはそのサイトへの信頼や評価を少しずつ高めていきます。しかし、サイトの根幹に関わる部分を不用意に変更すると、この積み重ねがすべてリセットされてしまうことがあるのです。
特に、初心者が注意すべきなのは以下の3点です。
- 安易なドメイン名の変更
→サイトの「住所」が変わるため、評価がゼロになります - ページのURLを頻繁に変更する
→各ページの評価がリセットされ、リンク切れの原因になります - サイト全体のデザインや構造の大幅な変更
→Googleがサイトを再評価するのに時間がかかり、一時的に順位が大きく下がることがあります
これらの作業は、ビジネス上の明確な理由がない限り、むやみに行うべきではありません。
もし何らかの理由で変更が必要なときは、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。
知識や操作に不安を持ちながら自分で行った場合、取り返しのつかないトラブルにつながる恐れがあります。無理に自分で対応せず、安心して任せられるプロに相談するほうが、結果的にリスクを回避して、さらに時間やコストの節約にもなるでしょう。
正しい知識で、焦らず着実にホームページを育てよう

全5回にわたる「自分で始めるSEO講座【基礎編】SEOの仕組みを理解する」を、最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
この講座では、SEOの基本的な仕組みから、具体的な実践ポイント、そして避けるべき失敗例まで、初心者の方がまず知っておくべき知識を解説してきました。
たくさんの情報があり、難しく感じた部分もあったかもしれません。しかし、SEOにおいて最も大切なのは、常に「検索する人のために、役に立つサイトを誠実に作り、育てる」という、たった一つのシンプルな姿勢です。
失敗を恐れる必要はありません。本講座で得た知識を元に、焦らず、着実にホームページを育てていきましょう。

自分で始めるSEO講座
【基礎編】SEOの仕組みを理解する
ご自身の力でSEOを理解し実践していくために、SEOとは何なのか、基本から実践につながる考え方までを段階的に解説します。
【記事作成・監修】
WMSデジタルマーケティング分析室

この記事は、WEB集客コンサルタント(中小企業のサイト構築300件以上・コンサル500件以上)と、検索キーワードから記事を設計するコンテンツ企画担当者が中心となり監修しています。
その実践的な知見と、当社が20年以上蓄積したオーガニック検索の成功データを元に、コンテンツ・SEOライティングで10年以上の経験を持つ専門WEBライターが記事を執筆。専門知識も分かりやすく解説し、検索順位向上に貢献する情報としてお届けします。
▼「SEOの基礎」の全体像がわかる【入門ガイド】
SEOで確実に成果を出すには、個別の施策だけでなく「全体像」を理解することが重要です。SEOの知識を点ではなく線でつなげ、迷いなく対策を進めるために、ぜひ入門ガイドをあわせてご確認ください。