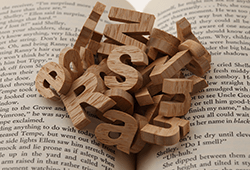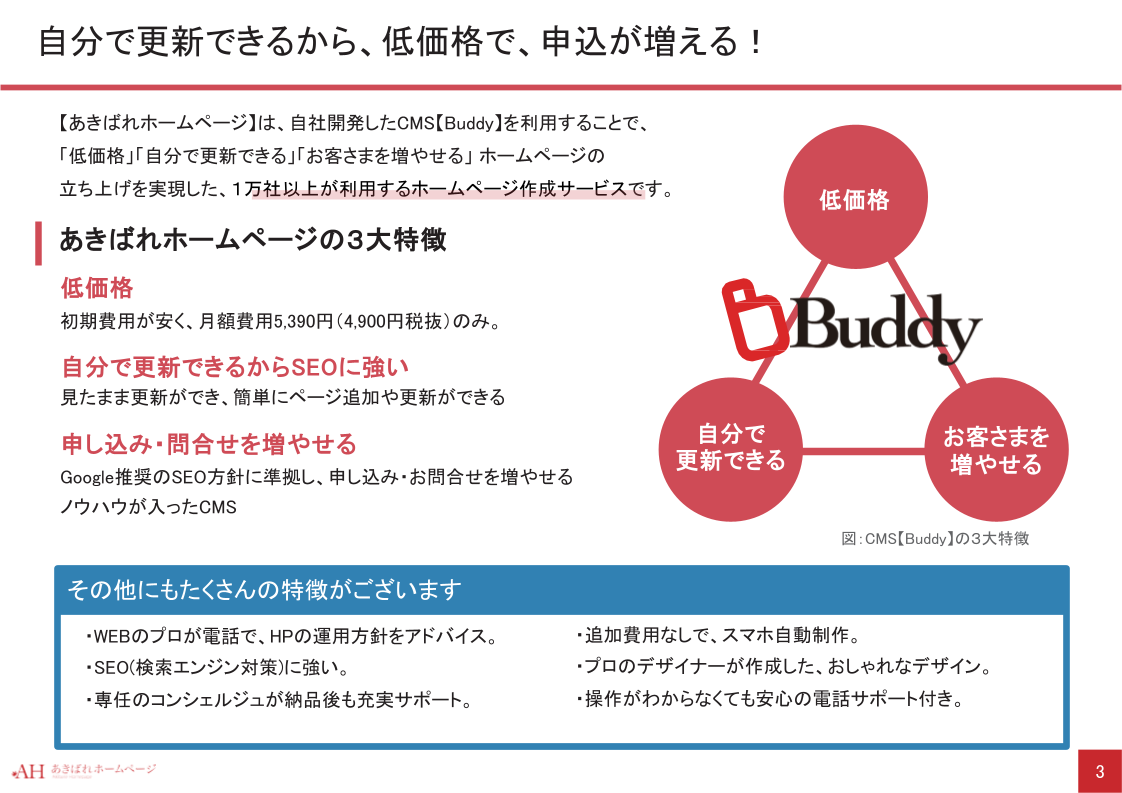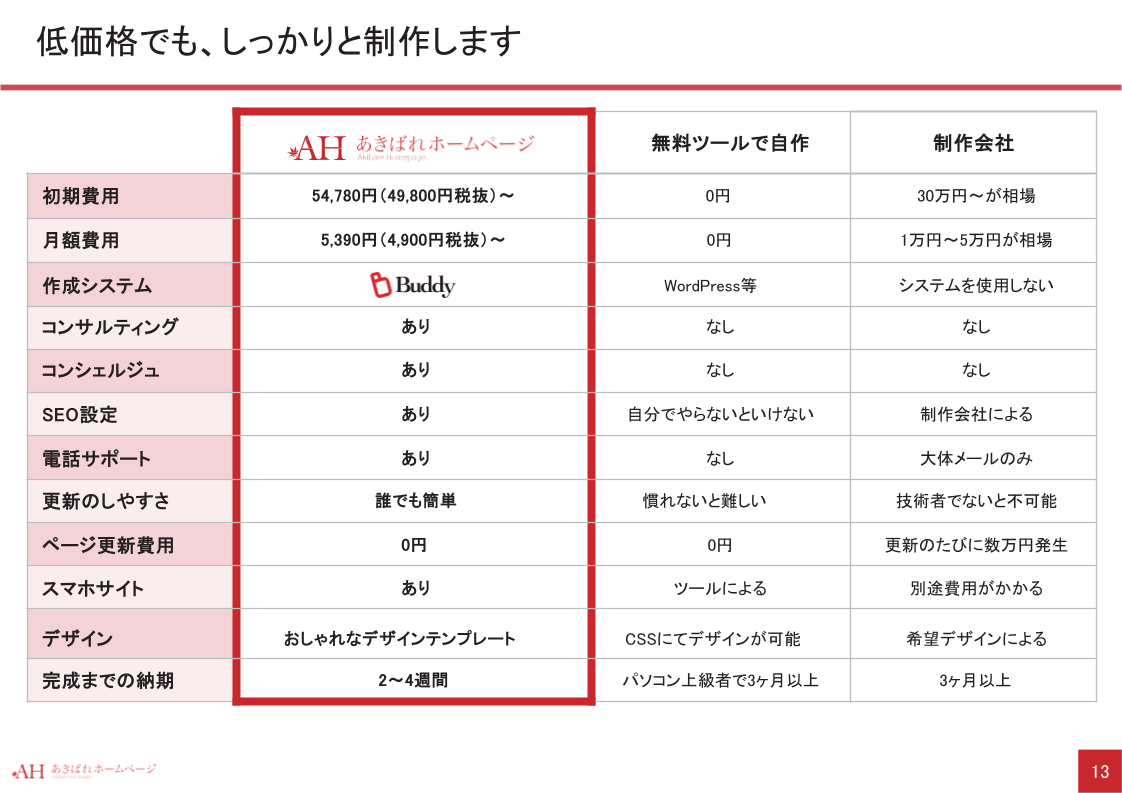ちゃんとわかってる?メリットとベネフィットの意味・使い方の違い
更新日:2024年4月22日

この記事では、ビジネスにおいて欠かせない「ベネフィット」について徹底的に解説し、あなたのビジネスがどのようにしてこれを駆使すれば顧客の心を掴み、市場での成功を収めることができるのかを順を追って説明します。
「メリット」と混同されがちですが、初心者でもすんなりと理解できるように、「ベネフィット」の基本的な定義から、具体的な活用法まで、なるべくわかりやすくお伝えしていきます。
また、実際のビジネスシーンでの事例を交えることで、ベネフィットの意識がどのように顧客満足度を高め、売上向上に直結するのかを具体的に掘り下げていきます。
この記事を通じて、ベネフィットの本質を理解し、あなたのビジネス戦略に活かしていただければ幸いです。
ベネフィットとは?
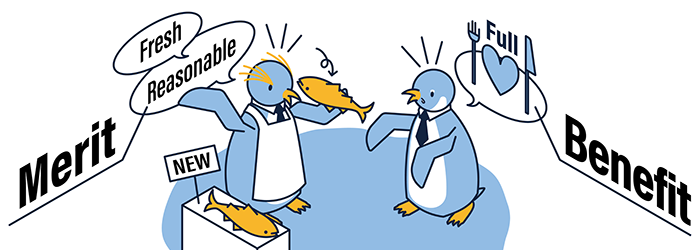
ビジネス(マーケティング)で使われる意味
ベネフィットとは、英語の「Benefit」であり、基本的な意味としては「利益」「特典」を指します。ビジネスの世界では、もう少し深い意味があり、顧客にとっての製品やサービスの真の価値を表す鍵となる概念です。
ひと言で言えば、ベネフィットは顧客が製品やサービスを利用することで得られる「利益」を意味します。しかし、この利益は単に物理的な特徴や機能に限定されるものではなく、顧客の感情や生活の質に深く関わってきます。大きくは3つに分けることができます。
| 種類 | 意味 |
|---|---|
| 機能的ベネフィット | これは製品やサービスが持つ基本的な機能や性能のことを指します。例えば、スマートフォンの場合、高速なプロセッサーや大容量のバッテリーが機能的ベネフィットにあたります。これらは製品を選択する際の直接的な基準となります。 |
| 情緒的ベネフィット | 製品やサービスを使用することで得られる感情的な満足感や幸福感です。これは、製品を通じて顧客が感じる安心感や所属感、特別な気持ちなど、目に見えない価値を含みます。
例えば、高級ブランドのバッグを持つことで高揚感を得られるのも、情緒的ベネフィットの一例です。 |
| 自己実現ベネフィット | このベネフィットは、顧客が自分自身の成長や目標達成に役立つ製品やサービスの利点を指します。例えば、オンライン学習プラットフォームが提供する知識やスキルの習得は、利用者のキャリアアップや個人的な成長に直結します。 |
各ベネフィットは、製品やサービスを顧客に選んでもらうための強力な動機付けとなります。そのため、ビジネスを運営するうえで、これらの概念を理解し、顧客に対して明確に伝えることが非常に重要です。
これらのベネフィットを意識して設計された製品やサービスは、顧客の心をつかみ、市場での成功を収めることがより可能になります。
ベネフィットをあなたのビジネスにどのように適用できるかを考えてみましょう。顧客が本当に価値を感じるのはどの点か、そしてそれを如何にして伝えるかが、成功を掴むためのポイントとなります。
情緒的ベネフィットの掘り下げ

ここでは情緒的ベネフィットについてより深く掘り下げていきます。
個室居酒屋が隠れた名店である場合、「おしゃれ」や「かっこいい」といった感情的なメリットが挙げられると思います。
おしゃれでかっこいい場所に行きたいと思っている人が多いため、感情的価値だけでお客様の「行きたい」を引き出せるのではと考える人も少なくないでしょう。
しかし、お客様が本当に求めているのは「おしゃれでかっこいい居酒屋」なのではありません。本当は「おしゃれでかっこいい居酒屋に彼女を連れて行く自分」や「おしゃれでかっこいい居酒屋で飲み食いする自分」を求めているのです。
人は他人に対する評価をほとんど気にしていません。自分に対する評価(自分はおしゃれでかっこいい)が何よりも大事です。
つまり、おしゃれでかっこいい居酒屋という感情的価値(メリット)から得られるベネフィットは「おしゃれでかっこいい自分を演出できる」とか「感情が高まる、気分が良い」といったもの。
この感情的価値からもベネフィットを生み出し、文章にすることでよりお客様を惹きつけやすくなるでしょう。
【混同されがち】「ベネフィット」と「メリット」の違い

ビジネスの世界では、製品やサービスの「メリット」と「ベネフィット」はしばしば混同されますが、これらふたつの概念には明確な違いがあります。
理解と適切な使用は、顧客とのコミュニケーションを改善し、製品やサービスの価値をより効果的に伝えるために不可欠です。
| メリット | 製品やサービスが持つ直接的な良い点、つまりその機能性や性能、特性を指します。これは製品やサービスが提供する具体的な特徴や機能であり、技術的な仕様、効率性、コスト削減などが含まれます。
例えば、ある洗剤が他の製品よりも30%多くの汚れを落とす能力があるというのは、その洗剤のメリットです。 |
|---|---|
| ベネフィット | ベネフィットは、そのメリットが顧客の生活や業務においてどのような価値をもたらすかを示します。つまり、製品やサービスが顧客の具体的なニーズや問題をどのように解決するか、または顧客の感情や生活の質にどのようにプラスの影響を与えるかを指します。
先の洗剤の例で言えば、そのベネフィットは「より少ない労力で衣類をきれいに保つことができる」という顧客の生活の質の向上にあります。 |
両者の違いを理解することは、顧客とのコミュニケーションにおいて極めて重要です。
多くのビジネスが製品やサービスのメリットに焦点を当てがちですが、顧客が本当に関心を持つのは、そのメリットが自分の生活や仕事にどのようなベネフィットをもたらしてくれるかです。
多くの人はお客様にメリットばかり伝えようとしがちです。しかし、お客様がメリットを知ったからといって商品やサービスを購入してくれるとは限りません。
人は意外と他人に対する評価なんてどうでもいいもので、それよりも自分への評価を気にする傾向があります。
つまり、その商品を手にしてお客様がどう変わるのか、何が得られるのかが一番の関心ごとなのです。この商品を使ってどういった良い変化があるのか、どんな利益があるのかを表す言葉が「ベネフィット」になります。
ベネフィットの類義語と対義語

ベネフィットを理解する上で、それに関連する言葉や概念を知ることも有効です。
特に、ベネフィットの類似語と対義語を把握することは、製品やサービスの価値をより豊かに、またはバランスよく伝えるのに役立ちます。
ベネフィットの【類似語】
価値
製品やサービスの持つ価値や重要性。これは、ベネフィットが顧客のニーズや欲求をどれだけ満たすかによって決まります。
魅力
製品やサービスが持つ魅力的な特徴や利点。顧客の注意を引き、興味を引き出す要素を指します。
これらの類似語は、ベネフィットを強調する別の方法として使うことができます。
それぞれが微妙に異なるニュアンスを持っているため、状況に応じて最適な言葉を選ぶことが重要です。
ベネフィットの【対義語】
不利益
製品やサービスを使用することで生じる可能性のある不利な結果や影響。
損失(ロス)
製品やサービスの使用から生じる損害や損失。これは、金銭的な損失だけでなく、時間や労力の無駄遣いも含むことがあります。
これらの対義語は、製品やサービスの全体像を正直に伝え、信頼を築くためにも重要です。
どんな製品やサービスも完璧ではなく、特定のデメリットや不利益が存在することを認識し、それらを「バランスよく伝える」ことが、長期的な顧客関係構築には不可欠です。
ベネフィットとその類似語を用いて、製品やサービスのポジティブな側面を強調し、一方で対義語を適切に使って、顧客に対して誠実かつ包括的な情報を提供することが、信頼と信用の構築につながります。
これは、特にWeb初心者のビジネス経営者にとって、オンライン上で顧客と効果的にコミュニケーションを取り、自社の製品やサービスを差別化する上で極めて重要です。
ベネフィットを見つける3ステップ

あなたのビジネスが提供する製品やサービスの真の価値を顧客に伝えるためには、まずはそのベネフィットを明確に理解することが必要です。
以下に、ベネフィットを見つけるための効果的なステップを紹介します。
STEP.1)ペルソナを作成する

ペルソナとは、理想の顧客像を具体的に定義したものです。年齢、性別、職業、興味、悩みなど、顧客の詳細なプロフィールを作成します。このプロセスを通じて、顧客のニーズや欲求、行動パターンを深く理解することができます。
ペルソナを定義することで、製品やサービスが満たすべき具体的な問題点が明確になり、それに基づいてベネフィットを考えることが可能になります。
【具体例】
あなたが運営するのは、小さなカフェです。理想の顧客(ペルソナ)は、地元のフリーランサー、秋晴ハナコです。ハナコは30歳で、快適な作業環境を求めています。
彼女のニーズには、高速Wi-Fi、静かな作業スペース、美味しいコーヒーがあります。マリアのペルソナを作成することで、彼女がカフェで何を求めているのかが明確になります。
STEP.2)商品の特徴・利点をリストアップする

あなたの提供する製品やサービスの特徴と直接的な利点を明確にしましょう。これには、技術的な仕様、使用のしやすさ、価格の優位性などが含まれます。
これらの特徴が、顧客にとってどのようなメリットをもたらすかを把握することが重要です。このリストアップ作業は、ベネフィットを洗い出すための基盤となります。
【具体例】
あなたのカフェが提供する特徴と利点は以下の通りです。
- 高速Wi-Fiサービス
- 静かで快適な作業スペース
- 地元産の新鮮なコーヒー豆を使用した多様なコーヒーメニュー
これらはカフェの直接的なメリットですが、ハナコのような顧客にとって、これらがどのようなベネフィットを提供するのかを考える必要があります。
STEP.3)利点に対するベネフィットを考える

各特徴や利点が顧客のどのようなニーズや欲求を満たすかを考えます。
ここで大切なのは、製品やサービスが提供する機能やメリットが顧客の生活や業務にどのようなプラスの影響を与えるかを具体的に理解することです。
【具体例】
高速Wi-Fiサービス
ベネフィット=ハナコはカフェでの作業効率が上がり、仕事の生産性を高めることができます。これにより、彼女は仕事に必要な時間を短縮し、プライベートの時間をより多く持つことができます。
静かで快適な作業スペース
ベネフィット=快適な環境はハナコにとって、ストレスを軽減し、集中力を高めることを可能にします。これにより、彼女は仕事の質を向上させ、満足感を得ることができます。
地元産の新鮮なコーヒー豆を使用した多様なコーヒーメニュー
ベネフィット=ハナコは新鮮で高品質のコーヒーを楽しむことができます。これは彼女にとって、日常の小さな贅沢であり、作業の合間のリフレッシュやモチベーションの向上につながります。
このように、各特徴や利点がハナコの具体的なニーズや欲求をどのように満たすかを考えることで、カフェはそのベネフィットを明確にし、マーケティングメッセージやサービス提供に活かすことができます。
顧客の視点からベネフィットを理解し伝えることで、カフェはハナコのような顧客にとって魅力的な選択肢となり、長期的な顧客関係を築くことが可能になります。
ベネフィットを中心にマーケティングやコミュニケーション戦略を構築することは、顧客の関心を引き、信頼関係を築く上で不可欠です。
ビジネスにおいて「ベネフィット」を伝える方法

ビジネスを成功させるためには、お客さんが製品やサービスを選択する際に直面する意思決定プロセスに影響を与える戦略が重要です。
ベネフィットを効果的に伝えることは、このプロセスを促進し、顧客の購買意欲を高める鍵となります。しかし、そのベネフィットをどのようにマーケティングに活かしていくかは難しい問題です。
以下に、具体例を用いて、ベネフィットの伝え方とその影響について解説し、成功事例を紹介します。今回は、「エコフレンドリーな洗剤の販売」を例に挙げて説明していきます。
(事例)エコフレンドリーな洗剤の販売

製品特徴
この洗剤は、環境に優しい成分のみを使用し、強力な洗浄力を持ち、またパッケージも再生可能な素材から作られています。
ベネフィットの伝え方
- ▼ 環境への影響
- 「私たちの製品を使うことで、あなたは地球にやさしい選択をしていると実感できます」
このメッセージは、環境保護への貢献という顧客の内面的な価値観に訴えかけます。 - ▼ 洗浄力
- 「強力な洗浄力で、頑固な汚れもすっきり」
このメッセージは、製品の実用性と効果を強調し、顧客の実用的なニーズを満たします。 - ▼ パッケージ
- 「再生可能なパッケージを採用しているため、使い終わった後も環境への負担を最小限に抑えます」これは、製品使用後の環境への影響を考える顧客にアピールします。
- ▼ 成功事例
- あるエコフレンドリーな洗剤ブランドは、SNSとWebサイトを通じて、上記のようなベネフィットを中心にしたマーケティングキャンペーンを展開しました。
特に、実際にこの洗剤を使用している人々の体験談や、製品が環境に与えるポジティブな影響に関するデータを共有することで、顧客の感情に訴えかけました。
- ▼ 結果
- このアプローチにより、ブランドは顧客の心を捉えることに成功しました。
顧客は自分が環境保護に貢献していると感じることができ、さらには強力な洗浄力という直接的な利益も体験できました。
この結果、売上は大幅に伸び、ブランドの認知度も向上しました。さらに、顧客からのポジティブなフィードバックがSNS上で共有されることで、新しい顧客層の獲得にも繋がりました。
この事例からわかるように、ベネフィットを中心にしたマーケティングメッセージは、顧客の意思決定プロセスに大きな影響を与えることができます。
製品やサービスの真の価値を顧客に伝え、彼らのニーズや価値観に訴えかけることで、ビジネスの成功を加速させることが可能になります。
まとめ

この記事を通じて、「ベネフィット」という概念の重要性と、それをビジネスにどのように適用し、成功に繋げるかについて深く掘り下げてきました。
ベネフィットは顧客が製品やサービスを選択する際に、単に機能や特性を超えた真の価値を見出すことを可能にします。
まずはペルソナを作成し、製品やサービスの具体的な特徴と直接的な利点をリストアップすることから始め、それらの特徴が顧客のどのようなニーズや欲求を満たすかを具体的に考えることで、ベネフィットを明確にすることができます。
こうして見つけたベネフィットを効果的に伝え顧客の心を捉え、売上とブランドの認知度を高めることができることができます。
今回紹介したステップやアプローチを活用し、あなたのビジネスが提供するユニークな価値を最大限に引き出し、顧客満足度を高めることで、競争の激しい市場で一歩リードすることができるでしょう。