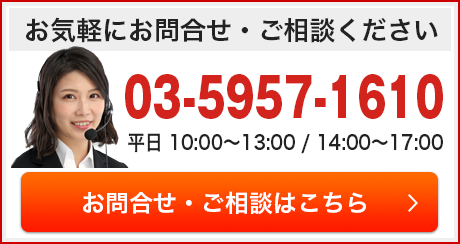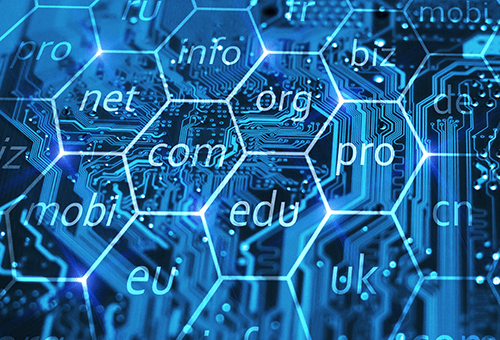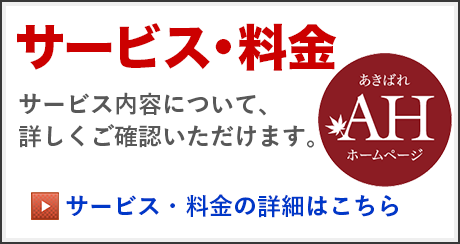【2025年版】格安ホームページ制作の費用相場は? 失敗しないための注意点と費用相場をプロが徹底解説

「できるだけ費用を抑えてホームページを作りたい。でも、『安かろう悪かろう』で後悔はしたくない…」
多くの方が抱えるこのお悩み、実は制作会社の選び方ひとつで解決できます。
格安を謳う業者の中には、「初期費用0円」の代わりに月額費用が高額だったり、サイトの所有権を渡してくれなかったりといった、思わぬ落とし穴が潜んでいることも少なくありません。
そこで本記事では、WEBマーケティングの専門家が、格安ホームページ制作のリアルな費用相場から、契約前に必ず確認すべき注意点までを徹底解説します。
この記事を最後まで読めば、悪質な業者を見抜き、予算内で質の高いホームページを手に入れるための具体的な方法がわかります。後悔しないホームページ制作の第一歩を、ここから踏み出しましょう。
格安ホームページ制作の費用相場はいくら?
依頼先・サイト種類別に解説

ホームページ制作の費用は、一般的に数十万円から数百万円と非常に幅広いですが、業者の選び方次第で5万円前後から作ることも不可能ではありません。
なぜなら、格安制作会社の多くは、デザインテンプレートの活用や人件費の削減といった企業努力によって、低価格なサービスを実現しているからです。
しかし、その安さの裏には料金体系のカラクリや注意点も潜んでいます。
まずは、一般的な相場と比較しながら「格安のホームページ制作費用」をサイトの種類別・依頼先別に詳しく見ていきましょう。
【サイト種類別】格安ホームページ制作の費用目安
ホームページの価格は、サイトのページ数や盛り込む機能によって大きく変わります。格安の制作会社は、デザインテンプレートの活用や業務の効率化によって、比較的小規模なサイトを低価格で提供することを得意としています。
ここでは、格安で依頼した場合の費用相場をサイトの種類別に見ていきましょう。
| サイトの種類 | 費用目安 | 主なページ構成・特徴 |
|---|---|---|
| 企業サイト | 5万円~30万円 | ページ数: 1~10ページ程度
名刺代わりとなる最低限の情報(会社概要、事業内容、お問い合わせ)を掲載するシンプルなサイトから、サービス内容や実績紹介まで含んだ基本的な構成のサイトまで制作が可能です。 |
| ランディングページ(LP) | 10万円~30万円 | ページ数: 1ページ
商品購入や資料請求といった、単一の目的を達成するために作られる縦長のページです。ユーザーの行動を促すための構成やデザインが重要になるため、1ページでも企業サイトより高額になる場合があります。 |
| ECサイト | 30万円~ | ページ数: 10ページ~
商品の登録・管理や決済機能など、専門的なシステムが必要です。格安プランの場合、デザインの自由度や搭載できる機能が限定的であることが一般的です。 |
格安制作会社は、主に「小規模」のサイト制作を得意としており、テンプレートの活用や業務効率化によって、この一般的な相場よりも大幅に安いプランを提供しています。
・企業サイトの費用について
近年、法人口座の開設審査などでホームページの提示を求められることもあり、「まずは名刺代わりのサイトが欲しい」という需要が非常に高まっています。
このようなニーズに応えるため、多くの格安制作会社が、数ページで構成されたシンプルな企業サイトを5万円〜10万円程度のプランで提供しています。基本的な情報をきちんと掲載したい場合でも、30万円以内の予算で十分満足のいくサイト制作が実現可能でしょう。
【制作会社例】
- ウェブプロ:6ページ構成で55,000円(税込)~
- スクーデリア・ノーベ:5ページ構成(フォーム含む)で55,000円(税込)~
- 株式会社ハイファクトリ:初期費用 39,800円(税込)~
このように、10万円以下で基本的な企業サイトを制作できるサービスも数多く存在します。
・ランディングページ(LP)の費用について
LPは1ページのみですが、訪問者に商品購入や問い合わせをしてもらう、という明確なゴールがあります。
そのため、ユーザーの心理を考慮したストーリー性のある構成や、クリックしたくなるデザインなど、専門的なノウハウが求められます。こうした理由から、シンプルな企業サイトよりも制作費用が高くなることも珍しくありません。
【制作会社例】
- ペライチ:ビジネスプラン 初期費用 0円、ビジネスプラン 月額 3,940円(税込)
- ホームページできるくん 初期費用 0円、月額1,900円(税抜)~
・ECサイトの費用について
ECサイトは、商品を販売するためのカート機能や決済システムの導入が不可欠です。これらの複雑な機能開発が必要となるため、他のサイトに比べて費用が高額になる傾向にあります。
格安で依頼する場合、利用できる決済方法が限られていたり、デザインのカスタマイズが難しかったりする可能性があります。もし初期費用を極限まで抑えたいのであれば、「BASE」や「STORES」のような無料で利用可能なASPカートを利用してご自身で作成する方法も有効な選択肢のひとつです。
※ASPカートシステムとは?
ネットショップを開設・運営するために必要な「買い物かご」や「商品管理」、「決済」などの機能を、インターネットを通じて利用できるサービスのことです。
【依頼先別】格安ホームページ制作の費用相場
制作を依頼する相手によっても、費用は大きく変わります。「制作会社」と「個人のフリーランス」、それぞれの格安相場と特徴を見ていきましょう。
・格安制作会社に依頼する場合
月額数千円から依頼できるサービスや、初期費用が数万円で済むプランが豊富にあります。
格安制作会社の料金体系は多様で、主に以下のパターンに分かれます。
- 初期費用+月額費用がかかるタイプ
- 初期費用が無料で月額費用がかかるタイプ
- 初期費用のみで月額費用が無料のタイプ
- 月額定額制(サブスクリプション型)のタイプ
例えば、「ホームページできるくん」は初期費用なし・月額1,980円から、「ZIUS」は初期費用33,000円・月額1,100円から といったサービスがあります。
ただし、「初期費用0円」を謳っていても、月額費用が高めに設定されていたり、契約期間に縛りがあったりするケースもあるため、年間コストで比較検討することが重要です。
また、安さには理由があることにも注意が必要です。格安制作会社の中にはサポート体制が整っておらず、電話での問い合わせが有料だったり、メールの返信が遅かったりするケースも少なくありません。
・個人のフリーランスに依頼する場合
企業サイトであれば15万円〜30万円程度が相場で、制作会社よりも費用を抑えられる傾向にあります。フリーランスは、事務所費用などの固定費がかからないため、その分を制作費に還元しやすいのが特徴です。
しかし、スキルや経験に個人差が大きく、品質が安定しにくいという側面もあります。途中で連絡が取れなくなったり、納品されなかったりといったトラブルのリスクもゼロではありません。
フリーランスに依頼する際は、クラウドワークスやランサーズといったプラットフォームを活用し、過去の実績や評価をしっかりと確認して、信頼できる人物か見極めることが不可欠です。
ちなみにホームページ制作では、誰に頼むかも重要ですが、目的に合ったサイトを作ることも同じように大切です。下記のページでは、目的に合わせたホームページ作成方法の選び方を解説しているので、併せてご覧ください。
目的に合わせたホームページ作成方法の選び方|経営者のための「HP作成講座」
見積もり前に知っておきたい!格安HP制作の料金体系

格安ホームページ制作の料金は、主に「初期制作費用」と「月額費用(ランニングコスト)」の2つで構成されています。しかし、会社によって料金体系はさまざまで、「初期費用0円」を謳うサービスもあれば、「月額無料」を掲げる制作会社も存在します。
一見安く見えても、トータルコストでは高くなってしまうケースもあるため注意が必要です。見積もりを依頼する前に、料金体系の全体像をしっかり理解しておきましょう。
初期制作費用
初期制作費用とは、ホームページのデザインや構築など、サイトを公開するまでにかかる費用のことです。格安制作会社の多くは、あらかじめサービス内容と料金が決まっている「パッケージプラン」を提供しています。
・パッケージプランの料金例(5万円前後〜)
多くの格安制作会社では、5万円前後から基本的なホームページが作れるプランが用意されています。
- ウェブプロ
6ページ構成で、55,000円(税込)
※月額費用なし
- 株式会社ハイファクトリ
初期費用:39,800円(税抜)~
※月額費用別途あり
- 株式会社スクーデリア・ノーベ
5ページ(お問い合わせフォーム含む)で、55,000円(税込)
- 合同会社いろどり
必要な機能がそろったパッケージが、55,000円(税込)
※月額費用は別途あり
- 株式会社 Rin Design
4ページのライトプランなら初期費用 49,800円(税込)~
※月額費用は別途あり
このように、名刺代わりのシンプルなサイトであれば、10万円以下の予算でも十分に制作を依頼することが可能です。
ちなみに【あきばれホームページ】の「初めてパック」なら、
- すぐ公開可能な5P+テンプレートページ9P、計14ページ、
- SEOコンサル込み
- ドメイン・サーバー設定サポート込み
- 最短10日納品
すべてコミコミで、初期費用は54,780円(税込)です。
・ポイント!「初期費用0円」や「制作費無料」の注意点
「初期費用0円」や「制作費無料」といった魅力的な言葉を掲げる制作会社もあります。初期投資を抑えられる大きなメリットがありますが、契約前には注意が必要です。
なぜなら、初期費用がかからない代わりに月額費用が高めに設定されていたり、最低契約期間の縛りがあったりするケースがあるためです。例えば、「初期費用無料・月額2万円(2年契約)」といったプランでは、総額で48万円の支払いが発生します。
目先の安さだけで判断せず、必ず年間コストや契約期間全体での総額を確認し、比較検討することが重要です。
月額費用(ランニングコスト)
月額費用は、制作したホームページをインターネット上で公開し、維持・管理していくために継続的に発生する費用です。主な内訳は以下の通りです。
1. サーバー・ドメインの維持管理費
ホームページを公開するためには、データを保管する「サーバー」と、インターネット上の住所となる「ドメイン」が不可欠です。月額費用には、これらの維持・管理にかかる費用が含まれていることが一般的です。
2. 保守・運用サポート費用
ホームページ公開後のテキスト修正や画像の差し替え、システムのアップデート、操作に関する問い合わせ対応など、運用をサポートするための費用です。サポートの範囲は制作会社やプランによって大きく異なります。
【月額無料のメリット・デメリット】
制作会社の中には、「ウェブプロ」のように納品後の月額費用が一切かからないサービスもあります。ランニングコストを抑えられるのが最大のメリットです。
一方で、「月額無料」の場合は公開後のサポートが全く期待できない可能性も指摘されています。例えば、サイトに不具合が生じた際の修正が有料対応になる、あるいは対応してもらえないといったケースも考えられます。
その他、追加で発生する可能性のある費用
基本のプランに含まれていない作業を依頼する場合、別途オプション料金が発生することがあります。
・サーバー・ドメインの新規取得費用
月額費用にサーバー・ドメインの維持費が含まれていても、新規で取得する際の実費は顧客負担となるケースがあります。目安として、レンタルサーバーは年間約5,000円〜16,000円、独自ドメインは年間約1,000円〜6,000円程度かかります。
・ 特殊なカスタマイズやオプション機能の追加
格安ホームページ制作は、テンプレートを基に作成することで低価格を実現していることがほとんどです。そのため、テンプレートの仕様にない特殊なカスタマイズや機能追加を希望する場合、別途見積もりとなることがあります。
・ページボリュームの超過
プランで定められたページ数を超えてページを追加する場合や、1ページあたりのコンテンツ量が想定されているボリュームを大幅に超える場合には、追加費用が発生することがあります。
【契約前に要チェック】格安ホームページ制作会社選びで失敗しないための8つの注意点

格安でホームページを制作できる会社は非常に魅力的ですが、価格の安さだけで選んでしまうと、「思っていたサイトと違う」「追加費用で結局高額になった」といった失敗につながる可能性があります。契約後に後悔しないためにも、発注前に確認しておくべき注意点を8つのポイントに分けて解説します。
料金・契約に関する注意点
まずは、トラブルになりやすい料金や契約内容に関する注意点です。表面的な価格だけでなく、その内訳や契約条件までしっかりと確認しましょう。
1. ランニングコストを含めた年間総額で費用を比較する
「初期費用0円」「制作費無料」といった言葉は非常に魅力的ですが、注意が必要です。
なぜなら、「初期費用がかからない代わりに月々の運用費用が高額に設定されている」ケースが多く、結果的に年間の総支払額が高くなってしまうことがあるからです。
具体例:どちらが本当に「お得」?
A社: 初期費用0円、月額費用 15,000円(2年契約)
B社: 初期費用 150,000円、月額費用 5,000円(2年契約)
一見、初期費用がかからないA社が魅力的に見えます。しかし、2年間の総額を計算してみましょう。
A社: 15,000円 × 24ヶ月 = 360,000円
B社: 150,000円 + (5,000円 × 24ヶ月) = 270,000円
この場合、2年間で9万円もの差が出ます。初期費用の安さに惑わされず、必ず「(初期費用)+(月額費用 × 契約月数)」で計算した総額で比較検討することが重要です。
2. ドメインの所有権が自社にあるか必ず確認する
ドメインとは、インターネット上の「住所」にあたる重要なものです。格安の制作会社に依頼する場合、この「ドメインの所有権が制作会社側になってしまうケース」があるため、契約前に必ず確認してください。
具体例:ドメインが「人質」になるケース
ある飲食店が、格安制作会社に依頼してお店のサイトを立ち上げました。数年後、より高機能な予約システムを導入するため、別の制作会社に乗り換えようとしました。
ところが、元の制作会社から「ドメインの所有権は弊社にあります。譲渡するには20万円かかります」と言われてしまいます。結局、高額な譲渡費用を支払うか、SEO評価や知名度を捨てて新しいドメインを取り直すかの苦渋の選択を迫られました。
ドメインは自社の資産です。必ず「契約者名義(所有権)が自社になるか」を契約書で確認しましょう。
3. 最低契約期間の縛りがないか確認する
月額制のプランを提供している制作会社の中には、「最低契約期間が設けられている場合」があります。
具体例:事業転換の足かせになる契約
ある企業が、新規事業のためにホームページを立ち上げました。初期費用が安かったため、深く考えずに「3年契約」を結んでしまいました。しかし半年後、事業がうまくいかず、方向転換を余儀なくされます。
ホームページはもはや不要になりましたが、契約期間が残っているため、あと2年半も使わないサイトのために月額料金を支払い続けることになってしまいました。
特に変化の速い業界では、長期の契約がリスクになることもあります。自社の事業計画と照らし合わせ、契約期間の有無とその長さを事前に確認することが不可欠です。
品質・サービスに関する注意点
次に、制作されるホームページの品質や、公開後のサポート体制に関するポイントです。安かろう悪かろうでは意味がありません。
4. テンプレートのみの対応ではないか確認する
多くの格安ホームページ制作会社は、あらかじめ用意されたテンプレートデザインを使用することで、コストを抑え、短納期を実現しています。それ自体は悪いことではありませんが、デメリットも理解しておく必要があります。
具体例:競合と「そっくり」なサイトに
ある士業事務所が、清潔感をアピールするテンプレートでサイトを制作しました。しかし、しばらくして近隣の同業他社も同じテンプレートを使い始めたため、ロゴと事務所名以外は瓜二つのサイトになってしまいました。これでは、顧客に独自性や専門性をアピールすることが難しくなります。
テンプレートは手軽ですが、デザインの自由度が低く、他社との差別化が困難になる可能性があります。どこまでデザインにこだわりたいかに合わせ、オリジナルデザインにも対応できる会社を検討しましょう。
5. 同業他社の制作実績が豊富かチェックする
制作会社を選ぶ際には、自社と同じ業界のホームページ制作実績が豊富かどうかを確認しましょう。業界への理解度は、サイトの成果に直結します。
具体例:業界理解の差が成果を分ける
ある歯科医院が、インプラント治療の集客を目的としたサイト制作を依頼しました。
- 成功例: 医療系に強いA社に依頼。A社は専門用語を分かりやすく解説するコンテンツや、治療への安心感を高めるための医師紹介ページの構成を熟知しており、問い合わせにつながるサイトを完成させた。
- 失敗例: 飲食店の制作実績しかないB社に依頼。見た目はおしゃれだが、医療広告ガイドラインへの配慮が欠けていたり、患者が求める情報(料金、治療期間、リスクなど)への導線が分かりにくかったりしたため、全く問い合わせが増えなかった。
単に実績の数を見るだけでなく、自社が求める目的(集客、採用強化など)を達成した具体的な成功事例があるかを確認することが重要です.
6. 公開後のサポート範囲(不具合対応など)を明確にする
ホームページは公開して終わりではなく、その後の運用が重要です。特に「月額費用無料」を謳う会社の場合、公開後のサポートが全く期待できない可能性があるため、注意が必要です。
具体例:「PHPエラー」でサイトが真っ白に
ある日突然、自社のWordPressで作成したサイトがエラーメッセージを表示して見えなくなりました。原因はサーバー側でPHPのバージョンが自動更新されたことによる、プラグインの互換性エラーでした。
制作会社に連絡すると、「納品後の不具合対応は有料です。調査と修正で最低5万円はかかります」との返答。結局、予期せぬ高額な出費が発生してしまいました。
「サーバーエラーへの対応」「WordPressやプラグインの更新代行」「軽微なテキスト修正」など、万が一の際にどこまで無償で対応してもらえるのか、サポートの具体的な範囲と料金体系を契約前に必ず明確にしておきましょう。
コミュニケーションに関する注意点
最後に、制作を円滑に進める上で欠かせないコミュニケーションに関するポイントです。
7. 制作会社側から打ち合わせの提案があるか
一部の格安制作会社では、制作工数を削減するために、打ち合わせを省略したり、簡単なメールだけでのやり取りのみで済ませようとしたりするケースがあります。
「お客さまの手を煩わせません」といった言葉には注意が必要です。
具体例:「思っていたのと違う」原因はヒアリング不足
発注者が「スタイリッシュでシンプルなサイトにしたい」とだけ伝え、制作会社はヒアリングをせずに制作を開始。完成したのは、情報が削られすぎて事業内容がほとんど伝わらない、ただの「空白が多いサイト」でした。
発注者の意図する「シンプル」と制作者の解釈が、打ち合わせ不足によって乖離してしまった典型例です。良い制作会社は、「なぜそうしたいのか」「それによって誰に何を伝えたいのか」という背景まで深掘りするために、積極的に打ち合わせを提案してくれます。
8. 担当者とのコミュニケーションは円滑に進められるか
いくら実績豊富な会社でも、担当者との相性が悪ければ、プロジェクトはスムーズに進みません。
具体例:「専門用語の壁」と「レスポンスの遅さ」
- 悪い担当者の例: こちらが「スマホで見やすくしたい」と伝えると、「レスポンシブ対応は当然ですが、コアウェブバイタルを意識したUI/UX設計が重要でして…」と専門用語を並べ立て、結局何をしてくれるのか分からない。メールの返信も3日後で、プロジェクトが停滞する。
- 良い担当者の例:「はい、スマホで見た時に文字やボタンが押しやすいように調整しますね。Googleの評価も高まるので、アクセスアップにも繋がりますよ」と、こちらの知識レベルに合わせて分かりやすく説明してくれる。質問への返信も迅速で、安心して任せられる。
契約前の問い合わせの段階から、担当者の説明の分かりやすさ、返信速度、ヒアリングの丁寧さなどを見極め、信頼できるパートナーかどうかを判断しましょう。
なぜこんなに安いの? 格安ホームページ制作のからくり

「ホームページ制作が数万円から」と聞くと、なぜそんなに安くできるのか不思議に思う方も多いでしょう。格安ホームページ制作には、主に3つの「からくり」が存在します。
その仕組みを理解することで、自社のニーズに合ったサービスかを見極めることができます。
人件費を削減しているから
ホームページ制作にかかる費用の大部分は、物理的な材料費ではなく「人件費」です。そのため、格安制作会社は様々な方法でこの人件費を削減しています。
まず、ホームページ制作は通常、ディレクター、デザイナー、エンジニアといった専門職がチームで行いますが、小規模な会社ではディレクターが開発業務を兼任することで、人件費を圧縮している場合があります。
また、クライアントとの打ち合わせ回数を最小限にしたり、メールでのやり取りのみに限定したりすることで、制作にかかる工数(時間)を削減し、低価格を実現しているケースもあります。
さらに、首都圏よりも人件費が安い地方の事業者へ開発を委託する「ニアショア」という手法や、フリーランスの専門家を活用することで、コストを最適化している会社も存在します。
テンプレートを活用して制作工数を削減しているから
多くの格安ホームページ制作会社が採用しているのが、あらかじめデザインやレイアウトが完成している「テンプレート」の活用です。
テンプレートを使用することで、ゼロからデザインを考えたり、コーディングを行ったりする必要がなくなり、制作にかかる時間と工数を大幅に削減できます。これにより、短納期かつ低価格でのサービス提供が可能になるのです。
ただし、テンプレートを使用する場合、制作会社によっては他社とデザインが似通ってしまう可能性がある点には注意が必要です。
サポート範囲を限定し、保守費用をなくしているから
「月額費用無料」「保守料なし」を謳う制作会社は、ホームページ公開後のサポート範囲を限定することで、ランニングコストを抑えています。
一般的な制作会社では、サーバーの管理やセキュリティ対策、サイトの不具合修正などを「保守管理」として月額費用に含んでいますが、格安制作会社の中にはこれらのサポートを提供しない、あるいは有料オプションとしている場合があります。
例えば、今回の記事で例に挙げている「ウェブプロ」さんでは、月額管理費が無料である代わりに、WordPressのアップデートなどに伴う公開後の不具合については原則対応しない(別途有料での相談は可能)という方針をとっています。依頼時には、あなたにとって必要なサポートがあるか必ず確認しておきましょう。
このように、納品後のサポートを必要最低限に絞ったり、更新作業などを必要な時だけ依頼するスポット対応にしたりすることで、月額無料という価格設定を実現しているのです。
ホームページ制作の費用をさらに抑える方法

格安ホームページ制作サービスを利用するだけでも費用は大幅に抑えられますが、さらにいくつかの工夫をすることで、コストを最小限にすることが可能です。ここでは、制作費用をさらに抑えるための3つの具体的な方法をご紹介します。
1. 「相見積もり」を取ってサービス内容と費用感を比較する
ホームページ制作会社を選ぶ際に最も重要なことのひとつが、複数の会社から見積もりを取る「相見積もり」です。
相見積もりを行うことで、各社のサービス内容と費用感を客観的に比較でき、自社の予算や目的に最も合った制作会社を見つけることができます。比較する際は、単に初期費用が安いかどうかだけでなく、以下の点にも注意しましょう。
- ランニングコストを含めた総額で比較する
初期費用が無料でも、月額の運用費用が高く設定されていたり、長期の契約期間が設けられていたりする場合があります。制作費用と月々の維持費用を合算したトータルコストで判断することが重要です。
- サービス内容とサポート範囲を確認する
格安の制作会社でも、サポート範囲は様々です。自社が求める機能(予約機能、SNS連携など)が含まれているか、公開後の更新や修正にどこまで対応してくれるかなど、サービスの詳細を比較検討しましょう。
2. 補助金(IT導入補助金など)を活用する
ホームページ制作には、国や地方自治体が提供する補助金を活用できる場合があります。補助金を利用することで、制作にかかる自己負担額を大幅に軽減できる可能性があります。
ホームページ制作で活用できる可能性のある主な補助金には、以下のようなものがあります。
| 種類 | 最大補助金額 | 補助率 |
|---|---|---|
| IT導入補助金 | 450万円 | 1/2 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 200万円 | 2/3 |
| 事業再構築補助金 | 1.5億円 | 1/2 |
- 小規模事業者持続化補助金 ※最も適している
販路開拓や業務効率化が目的。ECサイトやサービスの予約サイト、採用サイトなど、売上向上に繋がるホームページ制作に最適。
- IT導入補助金
EC機能や決済機能、予約機能などを持つITツール(ソフトウェア)の一部として導入する場合に対象となる。単なる会社紹介ページは対象外。
- 事業再構築補助金
事業の「再構築」という大きな取り組みの一部である必要あり。ホームページ作成単体での申請は不可。あくまで関連経費としての計上。
これらの補助金を利用する上で最も重要な注意点は、原則としてホームページ制作会社へ依頼する前に申請が必要であることです。
補助金制度は申請期間が限られている場合も多いため、制作会社の選定と並行して、利用可能な補助金がないか調べておくことをお勧めします。
3. テキストや画像素材を自分で用意する
多くの格安ホームページ制作サービスでは、サイトに掲載するテキスト(文章)や画像、写真といった素材は、基本的にお客様側で用意することが前提となっています。
例えば、制作会社によっては依頼時に「ホームページに掲載するテキストや画像等の素材」を用意するよう案内しているケースもあります。もし、文章作成(ライティング)や写真撮影を制作会社に依頼する場合、別途オプション料金が発生することが一般的です。
そのため、ホームページに掲載したい文章や写真を自社で準備することで、その分の費用を削減できます。もし自社で適切な画像を用意できない場合でも、制作会社によっては無料の素材集(フリー素材)から適切な画像を選んで代用してくれることもあります。
事前に掲載内容を整理し、必要な素材を揃えておくことは、スムーズな制作進行だけでなく、コスト削減にも繋がる有効な手段です。
まとめ:費用と品質のバランスを見極め、最適な制作会社を選ぼう

かつては高額な投資が必要だったホームページ制作は、今や誰にとっても身近なものになりました。テンプレートの活用やサポート範囲の工夫といった制作会社の努力により、数万円からという手頃な価格で自社の公式ホームページを持つことが可能となりました。
もちろん、「安い」というだけで安易に選ぶのは禁物です!
大切なのは、「何のためにホームページを作るのか」という目的を明確にし、初期費用だけでなく月額費用も合わせたトータルコストで比較検討することです。複数の会社から見積もりを取ってサービス内容をじっくり見比べれば、自社にぴったりの選択肢がきっと見つかるでしょう。
格安ホームページ制作は、賢く活用すればビジネスのスタートダッシュや新たな挑戦を力強く後押ししてくれる、頼もしい味方です。この記事を参考に、費用と品質のバランスが取れた最適なパートナーを見つけ、あなたのビジネスをさらに加速させましょう。
弊社が提供する【あきばれホームページ】は、費用と品質のバランスの良さが支持され、これまで12,000社以上のホームページを作成してまいりました。
もし、あなたがホームページの作成をお考えでしたら、ぜひご検討ください。